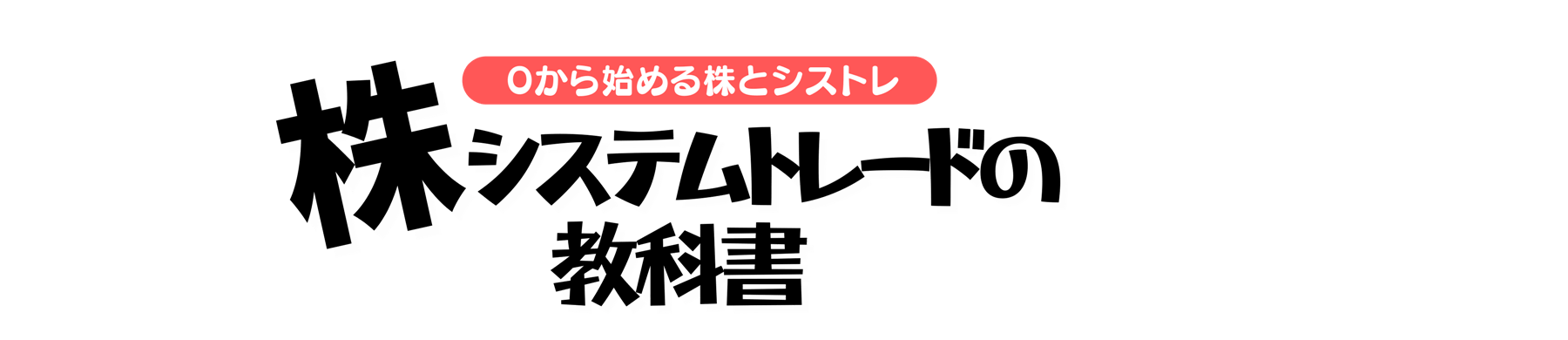目次
株の業種別特徴を押さえれば投資の手法が広がる
株式を選定する際は、自身の好みや割安感を基準にする方が多い傾向ですが、初心者はまず「業種ごとの特徴」を把握するのがおすすめです。
不況時の底堅さや株価変動要因が把握できるため、投資の手法を広げることに繋がるでしょう。
本記事では、各業種の特徴を詳しく解説するので、「難しくて理解しきれない」という方は、ぜひ参考にしてください。
日本市場17業種の特徴とは
ここからはさっそく、東証が定めた日本市場17種類の業種の特徴を解説します。
相場状況によって値動きの傾向が変わるため、ぜひ今後の投資に活用していきましょう。
エネルギー・資源
エネルギーと資源に関連する銘柄は、世界的な景気動向の影響を受けやすい特徴があります。
具体的には、景気が上向けば製造が加速化し資源価格も高騰、そしてさらに生産されていくという好循環が生まれるのです。
一方、社会情勢によってサプライチェーンが減速すると、エネルギー・資源の需要も後退しやすくなり、関連企業の株価もつられて安くなるでしょう。
医薬品
医薬品は市場の景気に関わらず需要が安定しているため、関連企業の株価も比較的安定性が高いといえるでしょう。
ただし、新薬開発に取り組む企業の場合、期待値によって買われているだけで、「実際は赤字経営」であるケースも多く、もし失敗すれば下落のトリガーにもなり得ます。
電気・精密機器
電気・精密機器は海外売上高比率が高い企業が多く、日本における内需よりも、海外の需要に影響を受けやすい傾向です。
また、海外企業が競合になるケースもあるため、市場分析の際は国内外双方の市況を観察しなければなりません。
機械
機械は完成品に加えて一部の部品、あるいは金型などを製造する企業に分かれており、主な取引国は中国が多い印象です。
投資家界隈では中国関連株と表現されることもあるため、中国国内の景気や金融政策には特に注意した方が良いでしょう。
さらに、一党制という性質上、特定の製品を規制する動きもスピーディーなので、頻繁に動向をチェックしておくのがおすすめです。
自動車・輸送機
自動車・輸送機は海外シェアが大きい業種の代表格といっても過言ではなく、特に米国は販売、製造ともに盛んです。
そのため、世界的な経済情勢や為替動向の影響を受けやすく、不安定な相場で利益を稼ぐこともできれば、損失を抱えがちなリスクもあります。
ただし、業界最大手のトヨタほどの規模になれば、そこまで株価が荒れる心配もないでしょう。
素材・化学
素材・化学は一見すると薬品に似ているように思えますが、どちらかといえばエネルギー・資源のような動きを見せます。
世界的な景気動向に影響を受けやすく、PERに関しても低水準になりがちです。
一方、特定の製品がヒットすれば、短中期的に高騰してテンバガーとなる期待も持てるでしょう。
鉄鋼・非鉄
鉄鋼・非鉄はそれ自体が製品として市場に出回るわけではないため、注目すべきは最終的な完成品の需要となります。
完成品がヒットすれば株価の高騰要因となりますが、景気後退で購買率が下がれば、当然下落してしまうでしょう。
電力・ガス
インフラ関連株である電力・ガスは、人が活きる上で必要不可欠であることから、景気に左右されにくい特徴があります。
したがって、短期ではなく中長期的なホールドが基本となっており、保守的な投資スタイルの方におすすめです。
商社・卸売
商社・卸売りは国内外の景気だけでなく、扱う製品の需要にも影響を受けるため、多角的な分析が要される業種といえます。
また、総合商社の商材は資源や鉱物と幅広いので、さらに視野を広げて市況を観察した方が良いでしょう。
比較的PERが低い特徴もあり、割安な銘柄が多い印象です。
情報通信サービスその他
携帯キャリアなどが当てはまる情報通信サービス業は、中長期に渡って安定した需要を確立しており、活動領域が国内に限られる点も投資しやすいポイントといえます。
少額投資では少し厳しいかもしれませんが、ある程度まとまった資金があるなら、配当金を狙った長期投資もおすすめです。
運輸・物流
インフラに関連する銘柄が多く、日本国内が主な市場となることから、為替リスクをほとんど考慮せずに投資が行えます。
事実、昨今のウイルスパンデミックでも、エッセンシャルワーカーとして認知されており、世界的な不景気をよそに、堅調な推移を見せました。
建築・資材
建築・資材は官民や通信工事、海洋関連と幅広いジャンルがあるため、様々な要因が価格変動を引き起こします。
ただし、全体的には比較的緩やかな推移となっており、基本的には台風などの天災に注意しておけば問題ないでしょう。
配当利回りが高めの銘柄も多く、初心者がチャレンジしやすい業種です。
銀行
銀行はローンや保険を取り扱う性質上、国の政策金利と景気によって株価が変動する特徴を持っています。
特に、低金利が続く昨今は業績が低迷する機関も多く、PERも全体的に低い傾向です。
金融
金融関連の企業も景気の影響を受けやすい印象ですが、銀行のように政策金利を気にする必要はほとんどありません。
そして、証券会社の株価は投資家が増えるほどに高騰しやすくなるため、昨今の投資ブームは好影響な流れといえるでしょう。
小売り
小売りは国内が主戦場となることから、基本的には日本マーケットをチェックしていれば問題ありません。
しかし、販売製品の輸入割合が高い場合は、為替リスクを考慮する必要があり、円安のタイミングでは業績が下振れしやすくなります。
実際のところ、2022年4月は1ドルあたり130円を目前にするほどの円安相場となっているため、今後の投資は慎重に立ち回った方が良いでしょう。
不動産
国内が主な市場となる不動産は、為替を考慮する必要がない反面、高額商品となることから、景気の影響を特に受けやすい業種です。
参考までに、不動産業界では「低金利」を売りにローンを勧めますが、銀行にとっては薄利多売な状況でもあり、もし景気が上向き金利が高くなれば、不動産にとっては不利になり得ます。
すなわち、両者はある程度相関性がある業種となるため、投資の際はぜひ参考にしてください。
食品
食品は景気に関わらず消費されることから、株価も比較的安定している特徴があります。
しかしながら、企業の数が大変多く、扱う製品もそれぞれ異なるため、スクリーニングをしっかり行って、将来性の見込める銘柄を見つけてみましょう。
株の業種別特徴を活かした投資戦略とは
ここまで解説した通り、株式は業種によって様々な特徴を持っており、相場状況によってまったく異なる値動きが発生します。
そのため、初心者はまずいくつかの業種をピックアップして、ポートフォリオを作成してみると良いでしょう。
たとえば、円安に強い機械関連の銘柄と、円高で有利な小売株といったように、性質が逆の業種を組み合わせるのもおすすめです。
さらに、少額ずつ資金を振り分けてバスケット買いを行えば、より価格変動リスクを抑えられるので、自分だけの投資戦略を組み立てていきましょう。
まとめ
本記事では、株の業種別特徴とおすすめの活用方法を解説してきました。
株式投資で効率的に資産を運用するには、株価や時価総額だけでなく、業種ごとの特徴を把握して、きちんと将来的な値動きも想定しなければなりません。
そして、ポートフォリオを作成すれば、単体銘柄に投資するよりも安全性が高まるため、今回触れた内容を参考に、さっそく投資戦略として取り入れてみてください。
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓
今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!