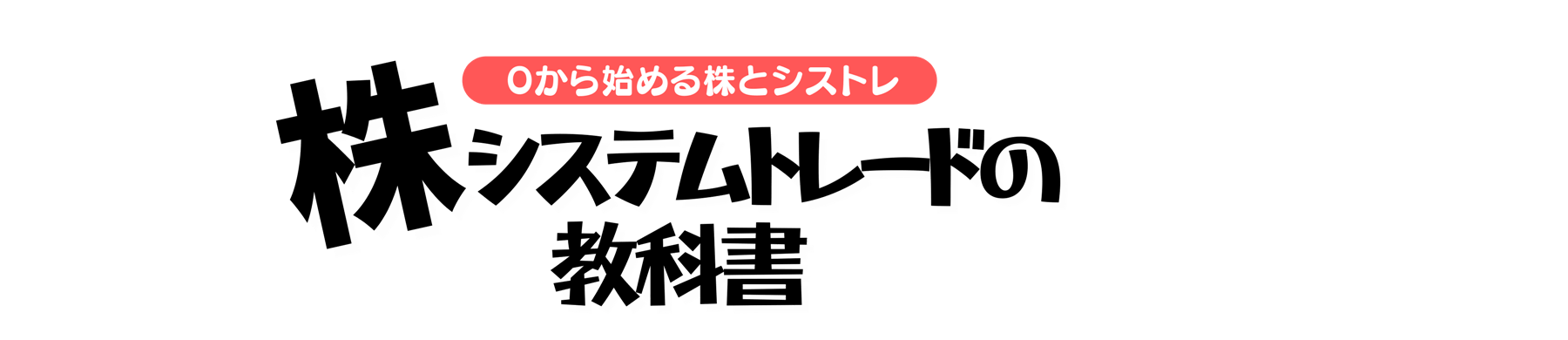目次
現物取引と信用取引の違い
現物取引とは、持っている資金の範囲内で株を購入する取引です。
現物取引では、買い注文しかできず、売りについては保有している株式を売ることしかできません。
一方、信用取引では、現金や株式、投資信託を担保にして、保証金の約3.3倍の取引ができます。また、売りから入る空売り(信用売り)も可能です。
信用取引をするには、通常の証券口座の開設に加えて、信用口座を開設しておく必要があります。
ただ、信用取引では、取引している銘柄が大暴落することによって、手持ち資金以上の損失が生じる「追証(おいしょう)」が発生するリスクもあります。
現物取引と信用取引の主な違いについて、表でまとめると次の通りです。
| 現物取引 | 信用取引 |
取引額 | 持っている資金の範囲内 | 保証金の約3.3倍まで |
取引に必要な口座 | 証券口座 | 証券口座、信用口座 |
最大損失額 | 投資金額まで | 追証が発生して保有資金以上の損失が出る可能性がある |
取引期間 | 無制限 | 6ヶ月(制度信用取引) |
空売り | できない | できる |
同一銘柄の1日の取引(日計り取引) | 現物買い→現物売りの1往復のみ | 何往復もできる |
手数料 | 現物手数料 | 信用手数料、金利 |
現物取引と信用取引の最大リスクについて
現物取引と信用取引の違いとして、最大リスクについては必ず押さえておきましょう。
現物取引では、投資している銘柄が上場廃止となってしまった場合が最大損失となります。
例えば、ある銘柄を現物取引で100万円買っていた場合に、上場廃止となってしまったら、損失額は100万円です。
一方、信用取引の最大リスクは、信用買いでは上場廃止となった場合に信用買いしている額まで、空売りでは理論上無限となります。
証券会社に預けている100万円の資金を担保に、信用買いで、ある銘柄を300万円買っていた場合に、上場廃止となってしまったら損失額は300万円です。
同様に、証券会社に預けている100万円の資金を担保に、信用売りで、ある銘柄を300万円空売りしていた場合には、その銘柄が急騰して何倍にもなった場合には300万円以上の損失が出ます。
※あくまで信用取引の最大リスクについての例示であり、実際には、委託保証金維持率30%を下回った段階で追証が発生するため、その前の段階で強制ロスカットとなります。
株のデイトレやスイングトレードにおける現物取引のデメリット
株のデイトレやスイングトレードにおける現物取引のデメリットについて見ていきましょう。
資金効率が低い
現物取引では、保有資金額までしか取引できないため、資金効率が低くなってしまう点がデメリットとして挙げられます。
特に、デイトレやスイングトレードの場合には、このデメリットは顕著です。
デイトレやスイングトレードのような短期投資では、ボラティリティー(値動き幅)が大きくなっている銘柄に集中投資することで、効率よく利益をあげられます。
例えば、資金が100万円の場合、勢いがある新興銘柄に集中投資でデイトレしたいとき、現物取引では100万円までしかトレードできませんが、信用取引では約330万円までトレードできます。
信用取引では資金の約3.3倍まで取引でき、リスクも相応に大きくなりますが、デイトレやスイングトレードでは早めの損切りを徹底していれば、そこまで大きなリスクにはなりません。
分散投資や増し玉がしづらい
現物取引では、取引額が自己資金までに制限されてしまうため、集中投資の効率が信用取引よりも悪くなることに加えて、分散投資や増し玉がしづらい点もデメリットとなります。
例えば、資金が100万円の場合、3銘柄に分散投資するとなると、現物取引では各33万円までしか投資できませんが、信用取引では各100万円ずつに分散投資できます。
デイトレやスイングトレードにおいて、有力銘柄が複数ある場合、それぞれにエントリーしたいとなると、信用取引の方が有利と言えます。
また、増し玉をする場合についても、やはり現物取引は信用取引に比べてデメリットがあります。
増し玉とは、エントリーした銘柄について、さらに取引して玉を大きくすることです。
例えば、ある銘柄を50万円買った後に上昇し、さらに大きく上昇すると期待したことから50万円を追加で買うといった行為です。
使える資金が大きくなる信用取引の方が、増し玉もしやすいことは言うまでもありません。
空売りができない
現物取引では空売り(信用売り)ができないため、デイトレやスイングトレードにおいてチャンスが半減してしまいます。
特に、数日から2週間程度の短期取引を行うスイングトレードにおいては、空売りができない点は大きなデメリットとなります。
例えば、2024年7月から8月初旬に掛けては、日銀利上げや米国市場でのAIバブル調整を背景に暴落相場となっていました。
このような時期には、買いで利益を出すことは難しい一方、空売りで利益を出しやすくなります。

下落相場において、現物取引の買いだけで利益を出すことは至難の業であり、むしろ何もしない方がマシであることも多々あります。
同一銘柄について反対売買しかできない
現物取引では、1日の中で、同一銘柄について反対売買しかできず、日計り取引は禁止されています。
例えば、資金100万円のとき、ある銘柄を9時00分の寄り付きで80万円買って、10時に全て売却してしまうと、その日は以後、その銘柄について取引ができなくなってしまいます。
一方、信用取引では、1日に何度でも取引できます。
例えば、次のようなことが可能です。
ある銘柄を寄り付きで買う
→10時に+1万円で利食いする
→その後に下落したため、後場寄り(12時30分)に再び買う
→大引け(15時30分)で+2万円で利食いする
長期投資においては現物取引が強い
デイトレやスイングトレードのような短期投資(トレード)においては、現物取引は信用取引に比べてデメリットが多くなっています。
一方で、長期投資においては、現物取引にメリットがあります。
制度信用取引には半年間の返済期限がある
現物取引には、返済期限がなく、一度買ったら、売るまで保有し続けることができます。
一方、制度信用取引では、約定日から6ヶ月後が返済期限となり、この日までに決済する必要があります。
配当利回りが3%以上の高配当銘柄や、S&P500指数やオルカン(全世界株株式)といったインデックス型のETFを長期投資する場合には、現物取引が絶対的におすすめです。
信用取引をすると金利が発生する
信用取引では、手数料に加えて信用金利が発生することも、長期投資におけるデメリットになります。
SBI証券における、現物取引と信用取引の手数料および信用金利は次のようになっています。
| 現物取引 | 信用取引 |
取引手数料 | 0円 | 0円 |
金利 | - | 買方金利:2.8% |
※参考:SBI証券「手数料」、SBI証券「国内株式信用のサービス概要」
SBI証券では、2023年10月からの「ゼロ革命」により、現物取引・信用取引の手数料がいずれも無料となりました。
つまり、現物取引で長期投資する場合には、取引手数料が完全無料です。
一方、信用取引の手数料も無料ですが、信用買いでは買方金利、空売りでは貸株料が発生します。
金利は、「金利÷(投資日数÷365日)」で発生し、デイトレやスイングトレードの場合には短くなるため、ほとんど気になりません。
例えば、100万円をデイトレで信用買いした場合には、100万円×「2.8%÷(1日÷365日)」=76円です。
一方、制度信用取引の返済期限である半年間(180日)に渡って投資した場合には、100万円×「2.8%÷(180日÷365日)」=13,808円となります。
まとめ
この記事では、株のデイトレやスイングトレードにおける、現物取引のデメリットについて解説してきました。
デイトレやスイングトレードといった短期投資においては、現物取引ではなく信用取引を使うことが合理的です。
信用取引で資金を約3.3倍大きく使えることは、集中投資や複数銘柄への分散投資、増し玉などで有利となります。
一方、長期投資においては、現物取引の方が有利です。
株式投資においては、デイトレやスイングトレードでは信用取引を使い、長期投資は現物取引で行うようにしましょう。
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓
今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!