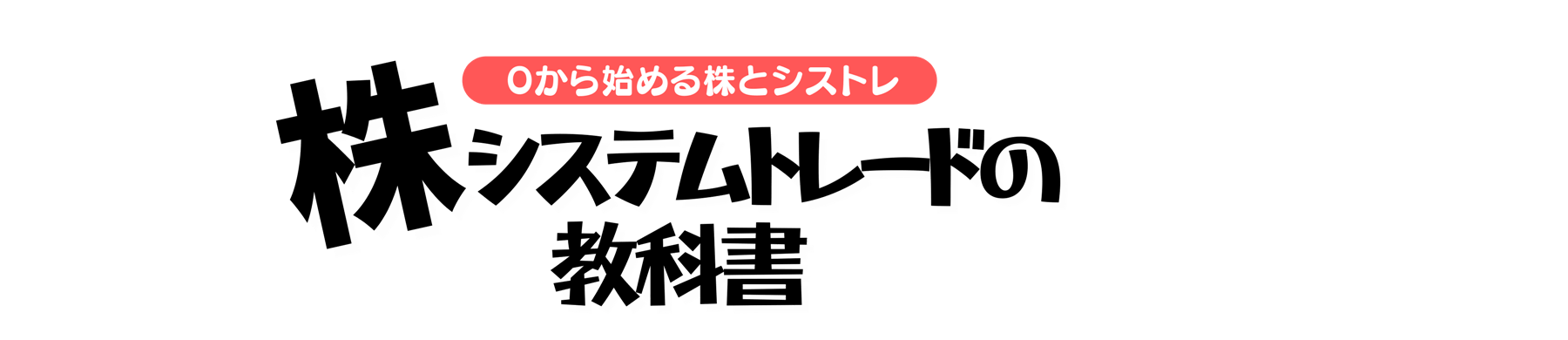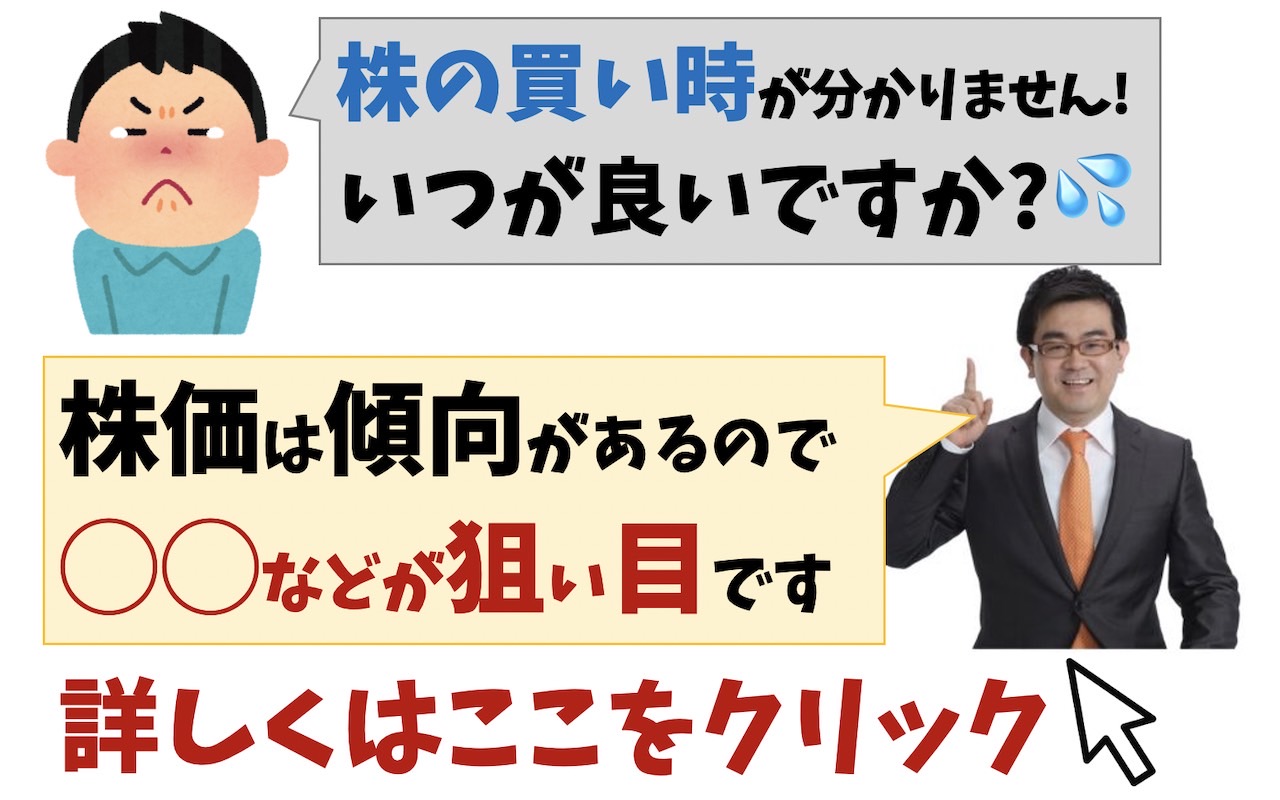目次
バスケット買いは初心者にもおすすめの投資戦略
株式投資には様々な戦略が存在しますが、その中でも特に損失をヘッジしやすいのが、「バスケット買い」です。
市場では主に大口機関投資家が用いている一方、10万円程度の少額運用でもチャレンジできるため、初心者にも大変おすすめといえるでしょう。
本記事では、バスケット買いの概要やメリット、注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
バスケット買いとは
ここからは、バスケット買いの概要と特徴について確認していきましょう。
- 複数の銘柄をまとめて売買する手法
- 少額投資でもチャレンジできる
それぞれ詳しく解説します。
複数の銘柄をまとめて売買する手法
株式投資における「バスケット買い」とは、複数の果物などをまとめておくカゴ(バスケット)が名称の由来となっており、様々な銘柄を一度に購入する手法です。
また、ほとんどの場合は、GPIF(日本年金機構)やファンドといった、大口機関投資家の売買を指しており、以下のような条件下で行われます。
- 1度に購入する株式は15銘柄以上
- 1億円以上の資金を投じる
すなわち、マーケットニュースなどで「バスケット買い」「バスケット取引」といった用語が登場する際は、基本的に大口の動向を示していると思って良いでしょう。
幅広いセクションに資金が行き渡ることから、相場を読み解く上でも重要な情報といえます。
少額投資でもチャレンジできる
先ほど触れた通り、バスケット買いは巨額の資金を保有する大口投資家の手法を指していますが、「複数の銘柄をまとめて購入」するという条件を満たせば、個人投資家であっても少額でチャレンジできます。
具体的に、100株で200円程度の低位株を10銘柄ほどピックアップし、ある程度まとまった数量を保有すると、スケール感がミニマイズされたバスケット買いが完成するのです。
実際のところ、1つの銘柄に資金を集中させるよりも損失リスクが低く、より多くの値上がりチャンスが掴めるため、初心者には特におすすめといえるでしょう。
大口のバスケット買いのポイント
大口によるバスケット買いは、巨額の資金が市場へ流入することから、個人投資家にとっても重要な価格変動要因になり得ます。
そこでここからは、大口が行うバスケット買いのポイントを見ていきましょう。
バスケット買いは立会外取引
基本的に、大口機関投資家によるバスケット買いはザラ場などの個人投資家が売買する時間ではなく、「立会外取引(通常時間外の取引)」によって行われます。
すなわち、市場が閉まっている間に数億円単位の資金が流れ込むことから、開場した後に強い値動きが発生するケースがあるのです。
したがって、たまたま保有していた銘柄に突然含み益が発生するチャンスである一方、事前に狙い撃ちするのはほぼ不可能といえるでしょう。
ただし、高騰の初動が掴めれば大きな利益が得られる可能性もあるため、こまめにスクリーニングを実施しつつ、マーケットニュースもきちんとチェックするのがおすすめです。
価格の下落を招く可能性もある
大口機関投資家は、買いだけでなく「バスケット売り」を行うケースもあり、相場の下落要因にもなり得るでしょう。
たとえば、決算期付近の現金化や、より安全な銘柄への資金移動は強い売り圧力となる上に、立会外取引によって不意に訪れるリスクもあります。
基本的に、市場が大混乱するような暴落が発生することはありませんが、短期的には含み損を抱える可能性もあることから、自身の銘柄を大口がバスケット買いで保有した際は、特に注意が必要です。
個人投資家がバスケット買いするメリット
ここからは、個人投資家がバスケット買いするメリットを解説します。
- 損失リスクを分散できる
- 幅広い利益チャンスが掴める
20万円程度の少額資金を運用している方は、ぜひ参考にしてください。
損失リスクを分散できる
個人投資家のバスケット買いは、安価な低位株を複数種類保有するため、一点集中のスタイルよりも損失リスクが抑えられます。
具体的に、Aという銘柄が下がったとしてもBが上がればトータルはプラマイゼロとなり、さらにCが高騰してくれれば利益が得られるでしょう。
分析スキルなどが身についていないうちに1つの銘柄に集中してしまうと、下落時のダメージが相対的に高まるため、将来性が見込める低位株をいくつか絞り込み、上手く資金を振り分けてみてください。
幅広い利益チャンスが掴める
効率的に幅広い利益チャンスが掴める点は、バスケット買いで得られる最大のメリットといえるでしょう。
また、数千種類もの中から値上がりが見込める銘柄をピンポイントで探し当てるのは、至難の業です。したがって、スクリーニングの確度と効率を上げるためにも、おすすめの手法となります。
加えて、同じセクションで固めるのも有効である一方、まったく別の業種に振り分けることもできるため、様々な戦略が試せるのもバスケット買いの魅力です。
個人投資家がバスケット買いする注意点
メリットが把握できたところで、次はバスケット買いの注意点についても解説します。
- 1銘柄あたりの利益は減る
- 20万円程度の資金が望ましい
より効率的に運用するためにも、きちんと押さえておきましょう。
1銘柄あたりの利益は減る
バスケット買いは資金を分散する性質上、1銘柄あたりの利益はどうしても減ってしまいます。
具体的に、20種類の銘柄を購入した場合は、単純に20分の1となるため、表面的な収支額は少し物足りないかもしれません。
しかしながら、一点集中で運用するよりも、損失額が抑制されることから、トータルで考えれば利点は多いといえるでしょう。
20万円程度の資金が望ましい
低位株に絞れば少額でもバスケット買いは行えますが、十分な数量を確保しつつ10~15銘柄に振り分けることを考慮すると、ある程度の資金は用意した方が良いでしょう。
実際のところ、5万円ほどでも振り分け自体はできる一方、1銘柄あたりの利益額は極端に減少してしまいます。
したがって、一定以上の収益性を確保するためにも、15~20万円程度は準備しておくのがおすすめです。
まとめ
本記事では、株式投資におけるバスケット買いの基本やポイントについて解説してきました。
バスケット買いは、大口機関投資家による複数銘柄の一括購入ですが、スケールを落とせば個人投資家でも実践できます。
損失リスクを抑制するためにも効果的な手法となるため、本記事を参考にぜひチャレンジしてみてください。
【無料】株システムトレードの教科書の記事は「システムトレードの達人」を使って検証しています。
↓↓↓↓↓
今ならシステムトレードの達人(無料版)がこちらよりダウンロードできます。
ぜひ手に入れてください!